ハゼ科
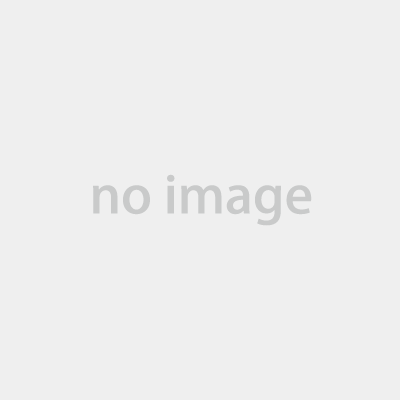
アカイソハゼ
全長3㎝。小型のハゼの仲間。沿岸の岩礁域に生息する。影となる岩の側面や隙間にいることが多い。眼の下に暗色の線模様があるのが特徴。
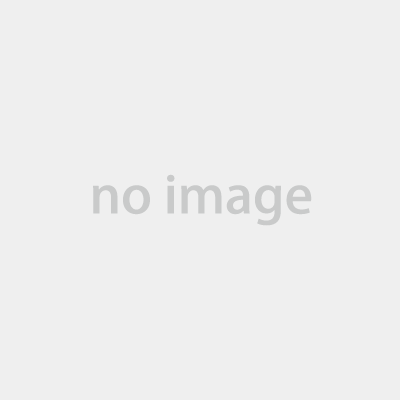
アカオビシマハゼ
沿岸の岩礁域や転石帯、港の防波堤や波消しブロックの隙間などに生息する。体側に暗色の縦帯が2本入が、体色は大きく変化し、縦帯が消えて横縞模様になることもある。
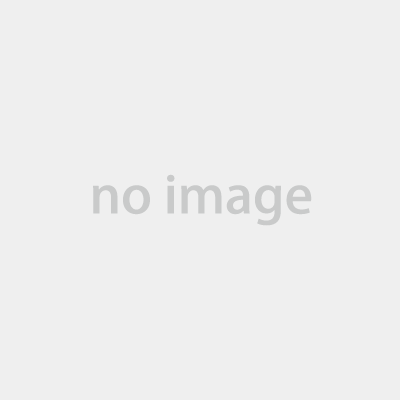
アゴハゼ
全長80mm。北海道から屋久島に分布。浅い岩礁地や大小の潮溜まりで普通に見られる。汽水域に入ることもある。灰色と茶色の体色で体側には白い斑点があり、胸鰭と尾鰭には細かな黒点があるのが特徴。
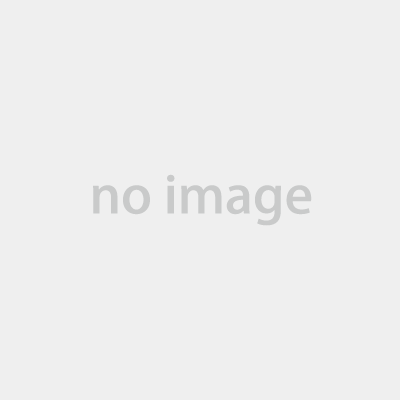
イソハゼ
全長3㎝。岩礁域やサンゴ礁域の水深1~15mで岩や礫の周辺に生息する。
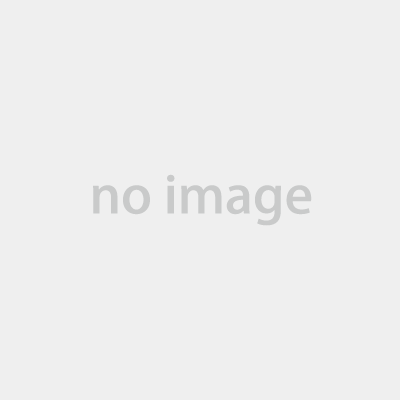
イチモンジハゼ
沿岸の岩礁域に生息し、岩壁の側面やオーバーハングした岩の下側などにくっついていることが多い。口元から眼を通り尾ビレまで続く暗色縦帯が1本と、眼の上に短い暗色の縦帯が1本ある。
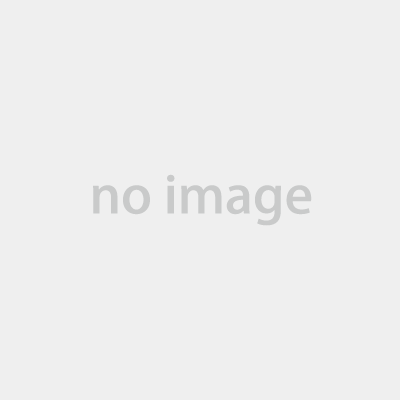
イトヒキハゼ
内湾や港内などの泥地や砂泥底の穴で、テッポウエビ類と一緒に生活している。第一背ビレに黒色斑がありスジは糸状に伸びる。眼の下側や後方に水色の斑点が散在する。
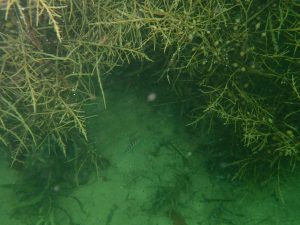
キヌバリ
アマモ場や岩礁地帯に生息する。本種は、日本海と太平洋に生息するもので色彩が大きく異なることが知られている。富山湾のものは、横縞が7本の日本海型である。ちなみに太平洋型は横縞が6本である。
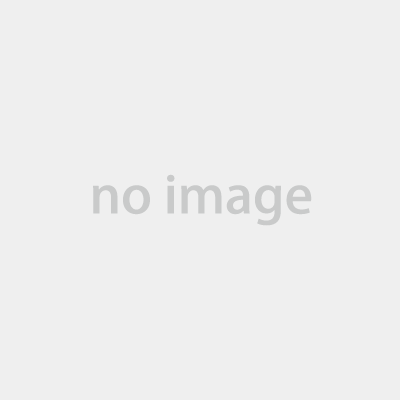
クツワハゼ
沿岸の砂地や転石帯、岩場などに生息する。眼の後ろに暗色の縦線が1本あるのが特徴。体側には赤茶色の斑点が散在する。

コモチジャコ
沿岸の水深20m以深の泥底に生息する。第一背ビレに大きな黒色斑がある。顎の下に3対のヒゲがある。小型の個体は体側中央に黒色の横帯が1本あるが、成長すると薄くなる。
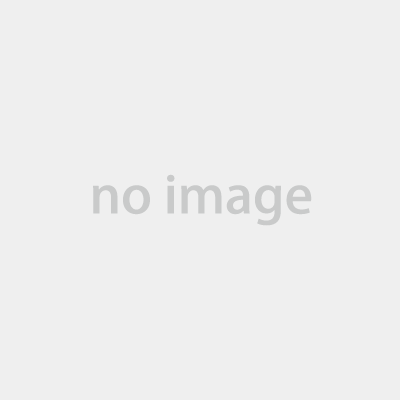
サビハゼ
浅場の砂底、泥底で生活する小型のハゼで、海水浴場やアマモ場、港内などでごく普通に見ることができる。第一背ビレの前縁と後縁には小さな黒斑が、また全身に茶色い斑紋が散在する。また、顎の下には特徴的なヒゲが多数生えている。
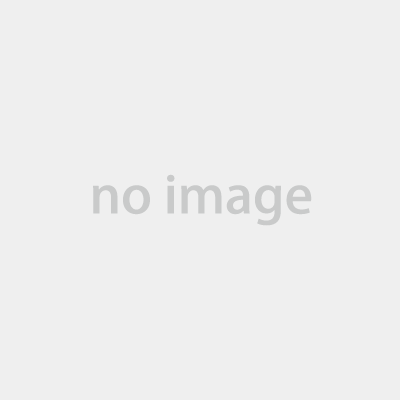
シロウオ
全長4~5㎝。幼形成熟で、成魚になっても体が透明。日本海型と太平洋型が知られている。内湾の浅海に生息。寿命は1年。
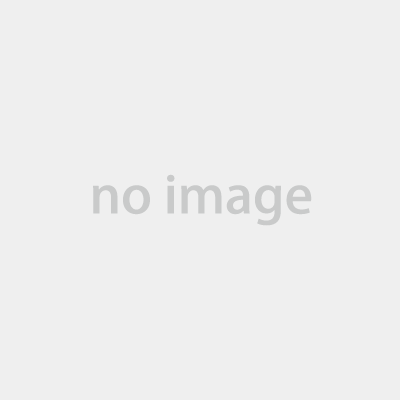
スジハゼ
内湾の砂底や砂泥底、アマモ場などに生息する。体側に暗色の細い縦縞があり、水色の小さな斑点が散在する。

チャガラ
アマモ場やガラモ場などで、常に群れで行動する遊泳性のハゼ。体側に6本の横縞、眼の上に1本の斜縞が入る。鮮やかなオレンジ色の姿は、とてもハゼとは思えない美しさである。富山湾では、夏から秋にかけて藻場や海水浴場、港内で見ることができる。

ドロメ
沿岸の岩礁域や転石帯、港内などに生息する。幼魚期は波打ち際に群れで浮遊して生活しているが、成長すると着底し海底で単独生活する。体は暗緑褐色で、白い斑点が散在する。尾ビレは白く縁取られる。
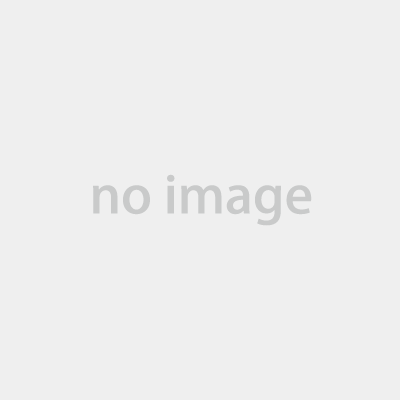
ニクハゼ
体長5㎝。内湾から河川の海の影響を受ける場所にかけて生息する。砂泥底の基質の上を群れで浮遊していることが多い。
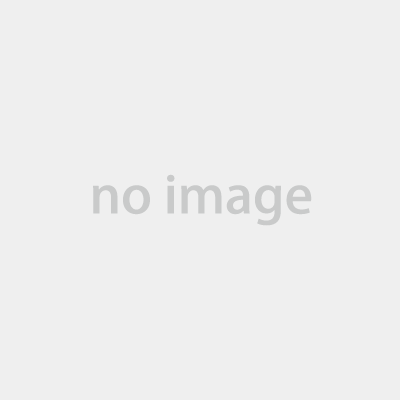
ニシキハゼ
全長20㎝。沿岸の岩場や砂地が入り混じった海底に生息する。体やヒレに黄色と水色の縦縞があり、とても美しい。
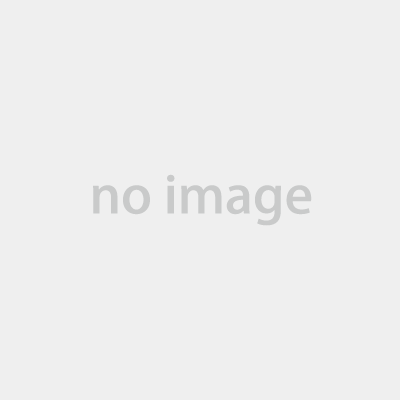
ヒメハゼ
砂底の浅場やアマモ場などで見られる小型のハゼ。背中に散在する斑紋はやや粗さを感じる。尾ビレの付け根にある黒斑はニ叉する。オスは第一背ビレの第二棘条が長く伸びるが、メスは伸びない。
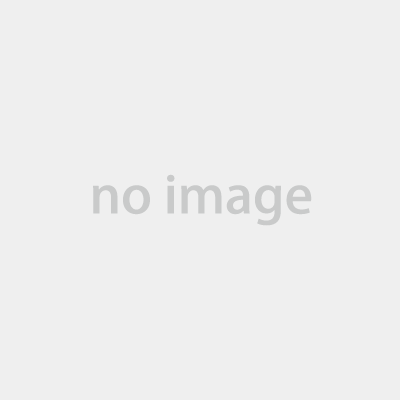
ホシノハゼ
港内など、穏やかな場所でよく見られる。体側には四角い斑紋が並び、頬にはうっすらと青い斜帯がある。オスは、第一背ビレに黒斑がある。富山湾では普通種だが、個体数はそれほど多くないと思われ、潜水していても、あまり出会わない。単独でいることが多く、人の姿を見かけると、遠くのほうまで一気に逃げていく。

マハゼ
日本各地に生息する最も一般的なハゼ。富山では、秋頃になると、流れの穏やかな河川の下流・河口域や港内などで見られる。非常に貪欲で、小魚や、エビ、カニなどあらゆるものを食べてしまうので、水族館では、同居魚の選定に気をつけている。寿命は1年程度だが、中には2年生き、全長25cmを超えるような個体もいる。



